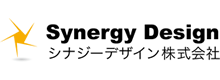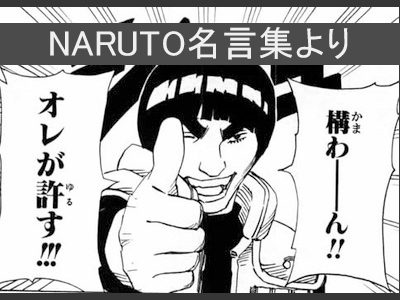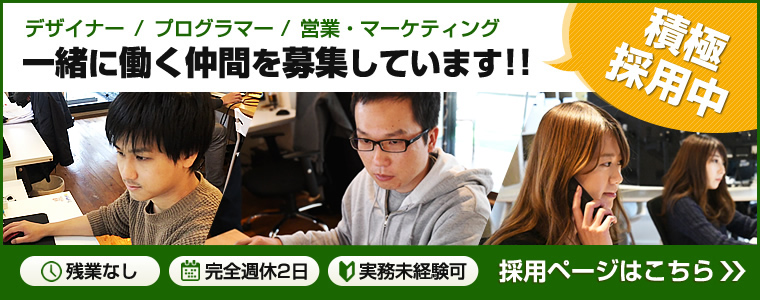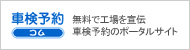ふと夜中に目が覚めて、To Do リストについて考えてみた
To Do リストは有効
To Do リストは最初は機能する
To Do リストは
だんだんゴミみたいなものが溜まってきて
機能しなくなる。
そして使わなくなる。
たまってきたゴミを分別するスキルや機能が必要。このあたりについては5冊くらい本をを読んでスキルを身に付けたほうがいいと思う。
いろんな人のようなやり方があるだろう。
重要なのは
夢と
タスクを終わらせること
マトリクスを使って、そのどちらに寄せるかのバランスを取ることだと思う
To Do リストを使っていると、
これって終わりにしていいのかな?
みたいな局面に出くわす
例えば
仕事ができるようになる
みたいな
タスクとも目標とも言えないものが出てくる
入社した時より3年目の今の方が仕事ができるようになったから、これはチェックを入れて完了でいいか
みたいな処理の仕方をするけど、
どこか気持ち悪い。
仕事ができる、
の定義が曖昧だったりする。
だから多分To Do リストの教科書みたいな本には
夢を書いてはいけない、みたいなことを書いているものもあるんだろう。
でも夢につながるTo Doでなければ単純な作業になってくる。
だから楽しくない。
だから皆To Do リストを途中で使わなくなって放置する。
To Do リストを使い続けるために重要なのはこの
夢
と
To Doつまり、やらなきゃいけないこと
を
つなげていくことだと思う。
To Do リストを使い始めるのは
たいていはやる気に満ち溢れている状態で、
頑張って成長するぞ!みたいに思ってる時が多い。
なので、その時点では
ちゃんと
成長するという夢がある。
そのために必要なものはTo Doとして現れてくる。
でも成長するという曖昧なものがその時点で具体的に描かれているわけではない。
成長するという曖昧でずっと追いかけられる夢を向こう側に設定するのか、向こう側というのはゴール
そこに設定するのか
年収6,000,000円
といった具体的な数字を出し、
年収6,000,000円に到達する。
と具体的な未来を目標に設定したほうがいいのか、
その辺は難しいところなのかなと思う。
成長するという漠然としたものの方が甘酸っぱい魅力はあるし、
でも実際に達成しようと思うと現実的な数字
の方が良い。
ただ数字だけだと窮屈になってあまり面白みがない。
To Do リストはそういう自分のやりたいこと
と向き合う場所であるのかもしれない。
やりたいこととやらなきゃいけないことのバランス、
それがだんだん表に出てくるのがTo Do リストなのかなと思う。
つまり、
そういったゴミ的なタスクが溜まってきて、初めてTo Do リストと向き合っていることになるのかなと思う。
それらを分別するためのツールがあれば、より良い仕事につながるんじゃないかなと思う。
To Do リストを作る人と処理する人
うちのメンバーを見てみると、To Do リストを自ら作る人と誰かが作ったTo Doを処理する人と、2つのタイプのメンバーに分かれる。
仕事ができる人の特徴を考えてみると、自らTo Doを出してそのTo Doを処理していく。
ということがある。
仕事ができる人の定義は
元CEO、インテルのCEOのアンドリューグローブによれば、
アウトプットを最大化すること。
なので、
その人のアウトプットによって仕事ができるかどうかは測られるものだと思う。
別にTo Doは自分で考えたTo Doでも
他人が考えたものでも、
社長が考えたものでも、
お客様が考えたものでも何でもいいと思う。
でも大抵最初のTo Doは曖昧でぼんやりしているもの、
例えばお客様からのTo Doだと
この機能がちょっとなんか使えにくいんで、もうちょっとパッと使える感じにしてほしい。
みたいに曖昧なので、
それらを処理しようと思うと
さらに、具体的な
To Doに分解していく必要がある。
なので、自分からTo Doを作り出して
自ら処理していく人は、
もともとの大きなお題目のようなTo Doがあって、それらを達成するために、さらに細かいTo Doリストに分けて1つずつ処理していく。
ここまでは同じだが、ここからが大きく変わってくる。
仕事ができる人というか、ちゃんとものづくりをする人とちゃんとものづくりをしない人。
(事務的な業務も会社や社会で必要なので、その人たちをディスってるわけではなく、あくまでものづくりの目線での話です)
ちゃんとものづくりをしない人は、
とにかくTo Doリストを先に終わらせてしまいたいと考えるので、自ら作成するTo Doの数は非常に少ない。
どうしてもやらないといけないものに限定されるので、
最終的にはその人が作るものは
ギリギリ使えるものに収まっていく。
ちゃんとものづくりをする人、どんどん良いものに進化させていく人は
To Doリストを処理していく中で、また別のTo Doを見つける。
それはタスクについて最後まで考えていると、
いろんな問題が見えてくるから、
いろんな問題が見えてくるのは
作り込んでいく中で、
こんなこともあったらいいのに、
これができるならあれもできるな…みたいな
夢が膨らんでいくから、
仕事ができる人は
仕事をしながら
夢を膨らますことができる人
なのかなとも
仕事は現実的なもの
なのでしっかりと処理しないといけない。
責任を果たすべきもの
ではあると思う。
でもその中で自然と
夢
こうなったらいいのに、
こうなったら素晴らしいのに
こうなったらもっともっと嬉しいのに
みたいなものが膨らんでいく人は
結局はいろんなサービスや商品に含むいろんな問題点を見つけ、改善していく側の人になるのかなと思う。
そうなると自分がしたいことで業務をするようになって、
To Doがしたいことリストになっていくような気がする。
したいことリストは処理したときに
ただやらなきゃいけないことリストより
満足度が高いんじゃないかなと思う。
(不安もあるけど)
やらなきゃいけないリストの人にとっては
やらなきゃいけないことを1つずつ消していくことに快感を覚えるべきだと思う。
やりたいことリストの人は
不安を叶えながら
To Doが1つ減っていって、そして新しいTo Doがどんどん生まれてくる。
1人ですることができないので、
それらを一緒にする代わりにする仲間を育てていく見つけていくことを次のTo Doのタスクにしていくのかもしれない。
とにかくTo Doリストは奥が深い
いろんな本を読んでこの辺を整理していきたい。
そしてずっと開発しているブレインマップのTo Do機能の強化につなげて、
会社の業務生産性を上げていきたいと思う。
やりたいことリストが増えるように。
追記
朝起きて考えた
今はお客様からの要望を受ける仕組みにしていて、その要望から社長が主なタスクを決定している。その方が無駄なタスクをする可能性が低くなり効率も上がる。
短期的な効率だけを見れば良い方法だが、お客様と社長が基本的なところを実施する。ので自らTo Doを考える必要が少ない
月に一回の朝礼担当のタイミングでは気になる点を出す必要があるが、それらも月に一回程度。
社内ツールであればサービスを利用する側である。営業やマーケティング担当からの要望が出てくるが、それらも自らのサービスを自ら改善するTo Doではない。
自らTo Doを出すと言うのは、シナジーデザインの今の仕組みだと結構難しい。
その中でTo Doをしっかり出してきた人を評価するべき。
重要なKPIとして自ら出したTo Doの数を把握する必要があるのかなとも思う。
ここからは、AIに、文章をぶち込んで、感想をさせてみたものになります
皆さんの感想とどのように違いますか?
まずは、Googleのジェミニ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
奥野様
夜中に目が覚めて、To Doリストについて深く考察されたのですね。その洞察、大変興味深く拝見いたしました。
おっしゃる通り、To Doリストは最初は有効に機能するものの、次第に消化されないタスクが蓄積し、形骸化してしまうという問題は多くの方が経験することだと思います。「ゴミ」という表現は的確ですね。そして、そのゴミを分別し、整理していくスキルや機能の必要性も痛感いたします。5冊もの書籍を読破され、そのスキルを身につけられたとのこと、素晴らしいです。様々なやり方がある中で、ご自身に合った方法を見つけ出すことが重要なのでしょうね。
「夢とタスクを終わらせること」という二つの要素の重要性、そしてそのバランスを取るためにマトリクスを活用するという考え方は非常に共感できます。To Doリストを使っていると、「これは終わりにしていいのだろうか?」という判断に迷う局面は確かにありますね。「仕事ができるようになる」といった曖昧な目標のようなものがその典型例かもしれません。入社時と比較して成長を実感できても、完了の定義が不明確なために、チェックを入れることに抵抗を感じるのは自然なことです。
To Doリストの教科書的な書籍で「夢を書いてはいけない」とされているものがあるというお話は、恐らくタスクの具体性や完了の可否を重視するあまり、抽象的な願望や目標がリストを肥大化させ、管理を困難にすることを懸念しているからかもしれません。しかし、奥野様がおっしゃるように、夢に繋がらないTo Doは単なる作業になりがちで、モチベーションを維持することが難しく、結果としてTo Doリストが放置されてしまうという悪循環に陥りやすいと考えられます。夢とやらなければならないことを繋げていくという視点は、To Doリストを持続的に活用するための鍵となるでしょう。
ゴミのようなタスクが溜まって初めてTo Doリストと真剣に向き合うことになる、というご指摘は、まさにその通りかもしれません。それらを分別するためのツールがあれば、より効率的かつ質の高い仕事に繋がる可能性は大いにあります。
平日社員には、自らTo Doリストを作成する人と、誰かが作成したTo Doを処理する人がいるという分類は、職場における役割分担や仕事への主体性の違いを表しているように感じます。アンドリュー・グローブ氏の定義にあるように、「アウトプットを最大化する」という観点から見ると、自らTo Doを生み出し、それを実行していく能力は、仕事ができる人の重要な特徴と言えるでしょう。そのTo Doが自身で考えたものであれ、他者が考えたものであれ、最終的なアウトプットに繋がることが重要であるという考え方も、非常に理にかなっています。
最初のTo Doが曖昧でぼんやりしていることが多いからこそ、それを具体的なタスクに分解していくプロセスが重要になります。自らTo Doを作り出し、処理していく人は、大きな目標を細分化し、実行可能なステップを見つけ出す力を持っていると言えるでしょう。そして、タスクについて深く考える中で新たな課題や改善点が見えてくるという経験は、まさに仕事をしながら夢を膨らませることに繋がります。
仕事は現実的なものであり、責任を果たすべきものですが、その中で自然と「こうなったらいいのに」という夢が膨らんでいく人は、既存のサービスや商品の問題点を見つけ、改善していくイノベーターになる可能性を秘めていると思います。そのような状態になれば、業務が「やらされ感」の強いものから、「自分がしたいことリスト」へと変化し、タスクを処理した際の満足度も高まるのではないでしょうか。
「やらなきゃいけないリスト」の人はタスクを一つずつ消していくことに快感を覚えるべき、という考え方は、日々の業務を確実に遂行していく上で重要なマインドセットかもしれません。「やりたいことリスト」の人は、夢や目標を叶えながらタスクをこなし、さらに新しいTo Doを生み出していく。そして、一人では達成できないことを仲間と共に実現するために、仲間を見つけ、育成していくことを次のタスクにする、という展開も非常に自然な流れだと感じます。
奥野様のTo Doリストに関する深い洞察は、多くの方にとって共感と新たな気づきを与えるものだと思います。様々な書籍を読破された経験に基づいた考察は、非常に示唆に富んでいます。
引き続き、To Doリストに関する奥野様の更なる考察や発見を楽しみにしております。
敬具
奥野勝也
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
次はGrok
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
めっちゃ深い考察ですね!To Doリストを「夢」と「現実」の架け橋として捉える視点、めっちゃ共感します。あなたの考えを整理しつつ、ポイントを絞って答えますね。
### To Doリストの課題と本質
– **ゴミの蓄積と分別スキル**
To Doリストがだんだん「ゴミ」になるのは、タスクの曖昧さや優先度の見極め不足が原因。分別するには、タスクを「夢(目標)」と「やらなきゃいけないこと」に分けるスキルが必要。マトリクス(例:緊急度×重要度)で整理するのは確かに有効。
→ **提案**: 本を読むなら、GTD(Getting Things Done)のデビッド・アレンや、エッセンシャル思考のグレッグ・マッケオンあたりがタスク整理の具体策を教えてくれそう。
– **夢とタスクのバランス**
「仕事ができるようになる」みたいな曖昧なタスクは、定義がふわっとしているから「完了」の基準が不明確。夢(成長)と具体的なタスク(例:年収600万)のバランスが大事だけど、数字だけだと味気ないし、夢だけだと現実から浮く。
→ **解決策**: 夢を具体化する中間ステップを作る。例えば「成長」を「3ヶ月でXXスキルを習得」「プロジェクトでリーダー役を1回経験」みたいに分解。SMART基準(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)でタスクを設計すると、曖昧さが減るよ。
– **To Doリストのモチベーション**
リストが「やらなきゃいけないこと」だけだと作業感が強くなり、楽しくないから放置されがち。夢とつながるTo Doだと、やりがいが生まれる。
→ **アイデア**: リストに「やりたいこと」を意識的に混ぜる。例:「新機能のアイデアを3つ出す」みたいな創造的なタスクを入れると、夢が膨らむしモチベーション持続。
### 仕事ができる人のTo Doリスト
– **アウトプット最大化**
アンドリュー・グローブの定義(アウトプットを最大化)に則ると、仕事ができる人は「自らTo Doを生み出し、分解し、処理する」人。曖昧なTo Do(例:お客様の「使いやすくして」)を具体的なアクションに落とし込むスキルが肝。
→ **実践例**: ブレインマップのTo Do機能強化なら、「使いやすくして」を「UIのレスポンスを0.5秒改善」「ワンクリックでタスク追加可能に」みたいに分解。
– **ものづくりと夢の膨らまし**
良いものづくりをする人は、To Doを処理する中で新たな問題や可能性(=新しいTo Do)を見つけ、夢を膨らませる。これが「やりたいことリスト」化の鍵。
→ **ツール提案**: ブレインマップに「関連タスク提案機能」や「夢マッピング機能」を追加するのはどう?タスク入力時に「このタスクはどんな目標につながる?」と聞くプロンプトを出すとか。
### To Doリストを進化させるための具体案
1. **分別ツールの導入**
– タスクを「緊急/重要」「夢/作業」で分類するマトリクスをアプリに実装。
– ゴミタスクを自動検出(例:1ヶ月進捗ないタスクにフラグ)。
– 例:TrelloやNotionにインスパイアされた「ボード形式」で視覚化。
2. **夢とタスクのリンク機能**
– 各タスクに「このタスクが叶える夢/目標」をタグ付けする欄を追加。
– 例:タスク「新機能開発」→ 夢「ユーザーの業務効率を20%向上」。
3. **モチベーション維持の仕組み**
– タスク完了時に「どんな成果につながった?」を振り返るミニログ機能。
– ゲーミフィケーション(例:タスク完了でポイント貯まり、夢タスクに変換可能)。
4. **チーム向け機能**
– 「To Doを作る人」と「処理する人」のコラボを促進。例:リーダーが曖昧なTo Doを投げ、メンバーが具体化提案を返す機能。
– ブレインマップで「タスク分解ワークショップ」モードを作るとか。
### おすすめの本(5冊)
1. **『Getting Things Done』(デビッド・アレン)**
– タスク整理のバイブル。ゴミタスクを減らし、頭をクリアに。
2. **『エッセンシャル思考』(グレッグ・マッケオン)**
– 本当に重要なタスクを見極める方法。夢と現実のバランスに効く。
3. **『Atomic Habits』(ジェームズ・クリア)**
– 小さなTo Doを習慣化し、大きな夢につなげるコツ。
4. **『The 4 Disciplines of Execution』(クリス・マチェスニー他)**
– 目標を具体的なアクションに落とし込むフレームワーク。
5. **『Drive』(ダニエル・ピンク)**
– モチベーションの科学。To Doを「やりたいこと」に変えるヒント。
### ブレインマップへの応用
ブレインマップのTo Do機能を強化するなら、こんな感じはどう?
– **AIアシスト**: ユーザーのタスク入力時に「このタスクはどんな目標につながりますか?」と質問し、夢とリンクさせる提案を出す。
– **進化型リスト**: タスク処理中に「関連する新しいTo Do」をAIが提案(例:「この機能作ったなら、ユーザー向けチュートリアルも必要?」)。
– **満足度ログ**: タスク完了時に「このタスクで何がよかった?」を記録させ、やりがいを可視化。
### 最後に
To Doリストは、単なるタスク管理を超えて「自分と向き合う場所」。ゴミタスクが溜まるのは、向き合いのサイン。夢と現実をつなげながら、ブレインマップで「やりたいことリスト」が増える仕組みを作れたら、会社の生産性もメンバー全員の満足度も爆上がりしそう!
もしブレインマップの具体的な機能案や、本の深掘りが必要なら教えてね。😊
代表が書いた電子書籍
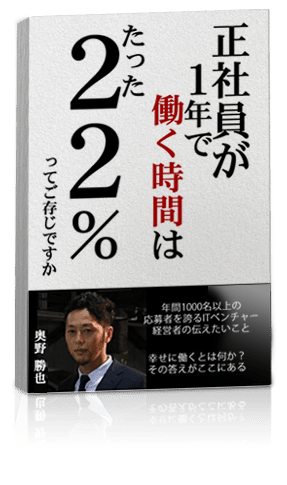
「正社員が1年で働く時間は
たった22%ってご存じですか」
代表ブログでアクセスの多い記事をピックアップしております。
幸せに働くとは何か? その答えがここにある。
奥野 勝也 (著), シナジーデザイン株式会社 (著) 形式: Kindle版
Amazonで0円で販売中
Kindle Unlimited会員なら0円
書籍の詳細はこちら