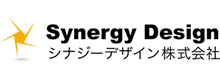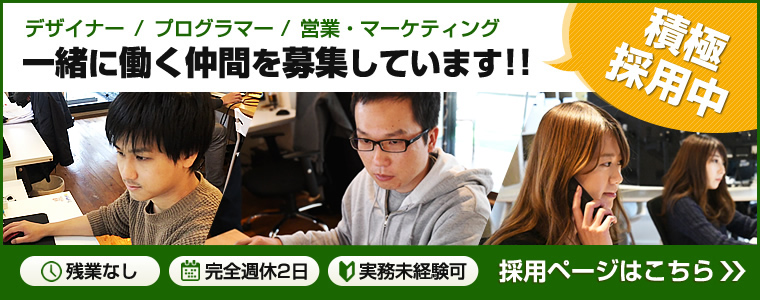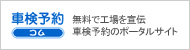こんにちは。
デザインチームのUです。
デザインチームでは現在、
弊社サービス「デキテル」の2025年度新デザインを制作中。
いくつかのデザインは完成前のフェーズに差しかかっており、
世に出せるものかを判断するための
品質(クオリティ)チェックをしている段階です。
今回、自身がクオリティチェックをしていて
問題点や感じたことを書いていきたいと思います。
チーム内のクオリティチェックをした直後に執筆しているので
多少厳しい内容になっているかもしれませんが
ご容赦いただければと思います。
油断をすると、自身でも陥りやすい部分でもあるので
自戒の意味も込めて書いていきます。
クオリティチェックで感じた問題点
今回クオリティチェックをしていて
かなりの数の差戻し数をを出しています。
具体的な数字でいうと70か所近くの数字。
技術的な部分を考慮しても、その数は減らせるはずです。
本来、クオリティチェックの段階で差戻しは出てはいけないもの。
と考えると、その数字の大きさがわかりますよね。
これだけ数が出ていると
「本気でこれをお客様に提供するつもり?」
と不安になります。
身近なサービスとして、飲食店を例にすると
盛り付けや味付けに問題があるものを
「お客様に提供していいですか?」
と聞いているようなものです。
できる範囲できれいに盛り付けましたや
できる範囲でおいしく味付けしましたは
お客様に通用しません。
まずは、
会社のサービスとして出せるものとして
クオリティチェックの依頼を出しているか。
と自分自身に問いかけてみる必要があるのかなと思います。
見た目を再現、は落とし穴
ここからは
クオリティチェックの内容から
さらに掘り下げて書いていきたいと思います。
結論から言うと原因は「戦略」だと思っています。
現在、デザインの制作とコーディングの実施は
フェーズを分けて着手していますが、
完全に切り替えてしまうと大きな事故につながります。
「コーディングでとにかく見た目を再現しよう」
というのは実は最悪で作業だけを行っている状態になります。
ベストな状態のデザインカンプを
ベストな条件下だけで組み立てていくので
それ以外の条件になったときに
エラーがでたり品質が落ちる原因につながります。
そして、現状では
見た目を再現する段階をゴール設定している状態になっていると推察できます。
そうなると当然差戻しが多くなります。
行き当たりばったりではなく、戦略を
見た目だけを再現しようとすると
コーディングも行き当たりばったりの対応になってきます。
そして、
指摘されたところだけを修正して、
また別の場所で問題がでて、、、
と悪循環に入ってしましまいます。
そうならないためにも、事前に戦略をたてる必要があります。
Aの時はBで対処する
Cの時はDで対処する
といったように
様々な条件下で最適に見えるよう
綿密に戦略をたてておくことが重要です。
細かい部分の仕上げはその後で十分。
かなり繊細でむずかしい部分にはなりますが、
デザイナーとして必要なスキルでもあります。
画像制作など他のタスクではできるようになってきているので
新デザイン制作でもできるようになると考えています。
普通にしていると淘汰される
最近はAI技術の発展なんかも話題になりますが、
世間、とりわけIT業界では目まぐるしいスピードで進化しています。
普通にしているだけじゃ淘汰されてしまうんですね。
先程ゴール設定の話をしましたが、
この辺りが前提にあれば
「自身が考えている品質」と「会社の求める品質」の大きな乖離は防げるかなと思います。
クリエイターとして乗り越えないといけない壁になるので、大変な段階ではなありますが、
成長し乗り越えられると、不要なストレスを感じなくなりますし
なにより自身の価値があがり給料もアップします。
当然、自分自身にもメリットがあることなので、乗り越えていきましょう。