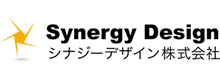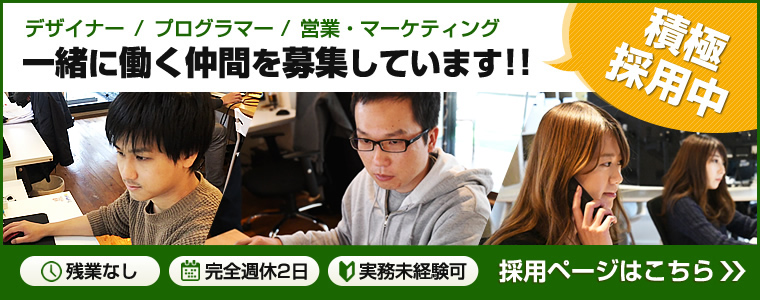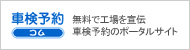こんにちは。マーケティングチームのSです。
最近、営業での熱意の重要性を感じることがあったのでそれについて記載したいと思います。
もちろん気持ちの問題、みたいに書くつもりはありません。営業はメンタル勝負、みたいな話は色々ありますが、重要なのはその前のマインドセットだと思います。
きっかけは、
あるビジネス本を読んだことなのですが、
某中古車販売チェーンの新人店長として就任して、県内最下位の売上をわずか1ヵ月で一位に急成長させた、という内容でした。
マーケティング戦略なども登場するのですが、
印象に残ったのは、著者の当時の圧倒的な熱量でした。
目標達成をするために、
誰よりも、元気に声を出し、機敏に動き回る。その姿が徐々に周りを動かしていき、負け組のメンバーたちに自信があふれ、結果が出始める、という内容でした。
人を動かす熱意
この書籍を読んで思ったことは、2つ。
一つは、営業成績で大事なことに、
売れる雰囲気がある。それが、声や機敏に動き回る姿なのだと思いました。
著者の情景描写は、当時の様子を臨場感あふれる姿でイメージさせるものでしたが、
読みながら想起されたのは、うちの代表の姿でした。
常に熱量にあふれ、社内も社外に対しても、人を動かす力という意味で同じものを感じました。
自分は昔からのクセで理屈っぽく考えがちですが、同じように、力溢れる姿、ノンバーバルな部分の重要性を感じました。
変化は言語化がもたらす
もう一つは、変化のプロセスです。
最下位の成績から、県内1位に。組織自体が大きく変化したわけですが、なぜ変化できたのか?
書籍内では2つの要素が登場しています。
1つは仕組み化、ボトルネックとなっている箇所を塞ぎ、効率的に営業成績を進める戦略を取ったことです。
もう1つが組織を2つに分けたことです。
ベテランチームと新人チームに分けて、店長は新人チームと組んで1ヵ月稼働をしています。
個人的には2つめが大事だと思いました。
なぜなら、小さなグループ内ではより密なコミュニケーションが行われるからです。
グループ内では著者の考えが言語化され、頻繁に共有されます。
チップ・ハース , ダン・ハース著『スイッチ!』では、
企業文化の変化について、実例を出しながら以下のように解説しています。
すべての文化はその言語によって強力に形づくられている。小さなグループ内での話し合いの機会は、変化の過程で改革の言語を生み出すことに大きく寄与する。
このようなグループ形成と、話し合いの習慣化が重要であると。
店長による変革はまさしく、一つの組織文化の変化の過程でしょう。しかも、入社して間もないメンバーであれば、変化はより容易かったと思われます。
営業成績には熱量が大事なこと、また、熱意あふれる人物が旗頭となり、話し合いの中で新しいアイデンティティを形成する。結果として、大きな成功を収める。
このような成功は非常に魅力的なサクセスストーリーです。
特に営業は成績が分かりやすい花形だと思うので、同じような結果が出せるように頑張りたいと思います。